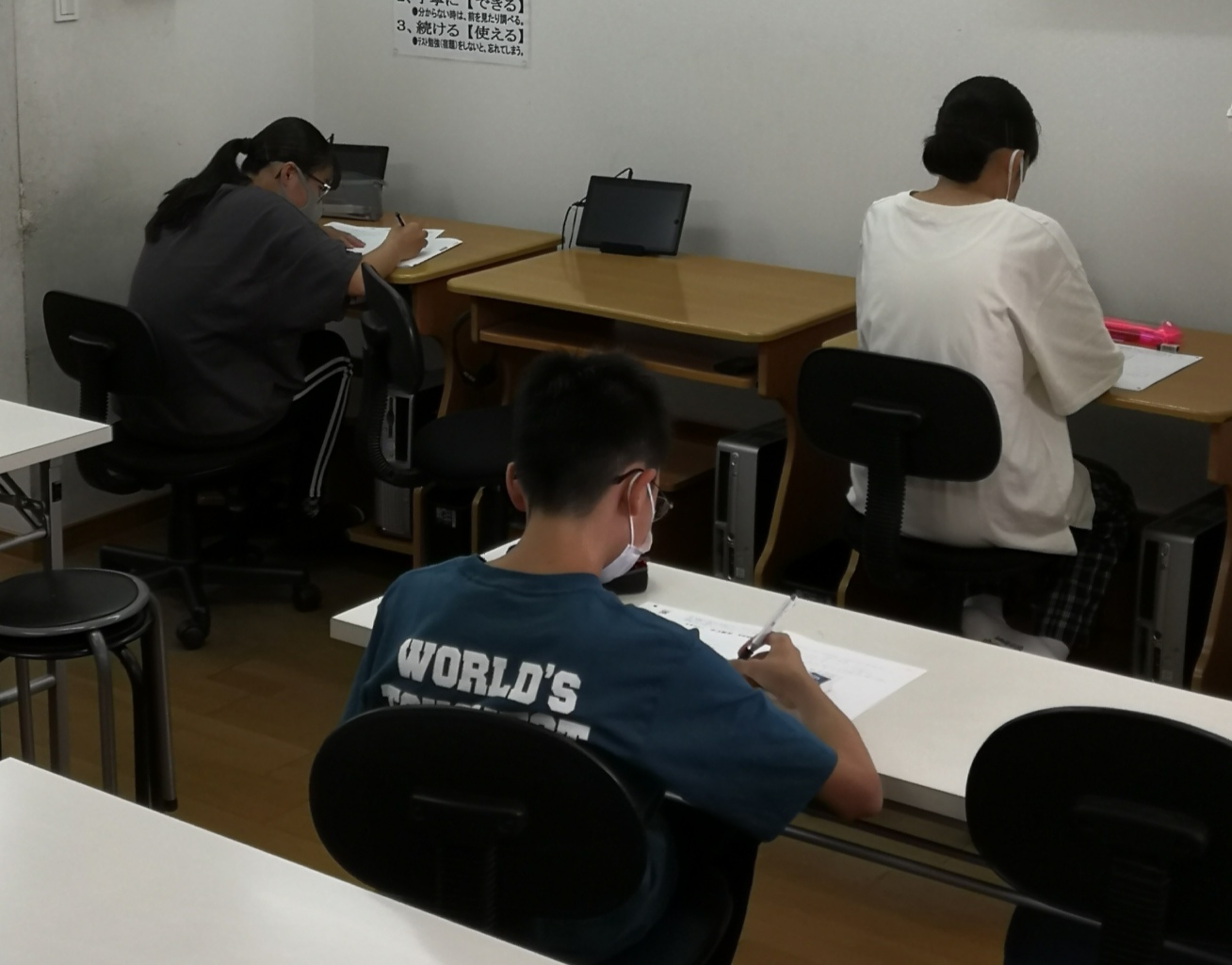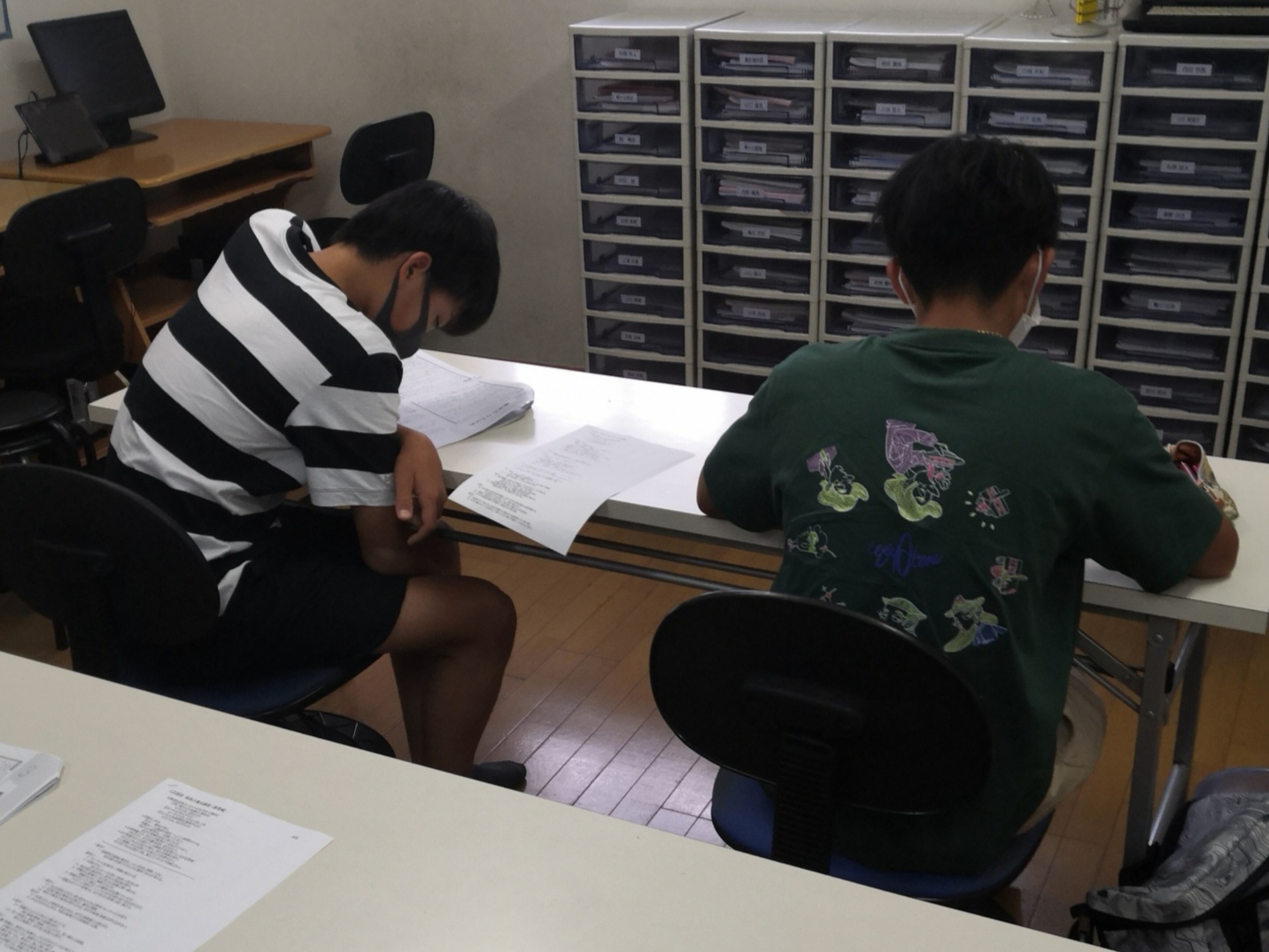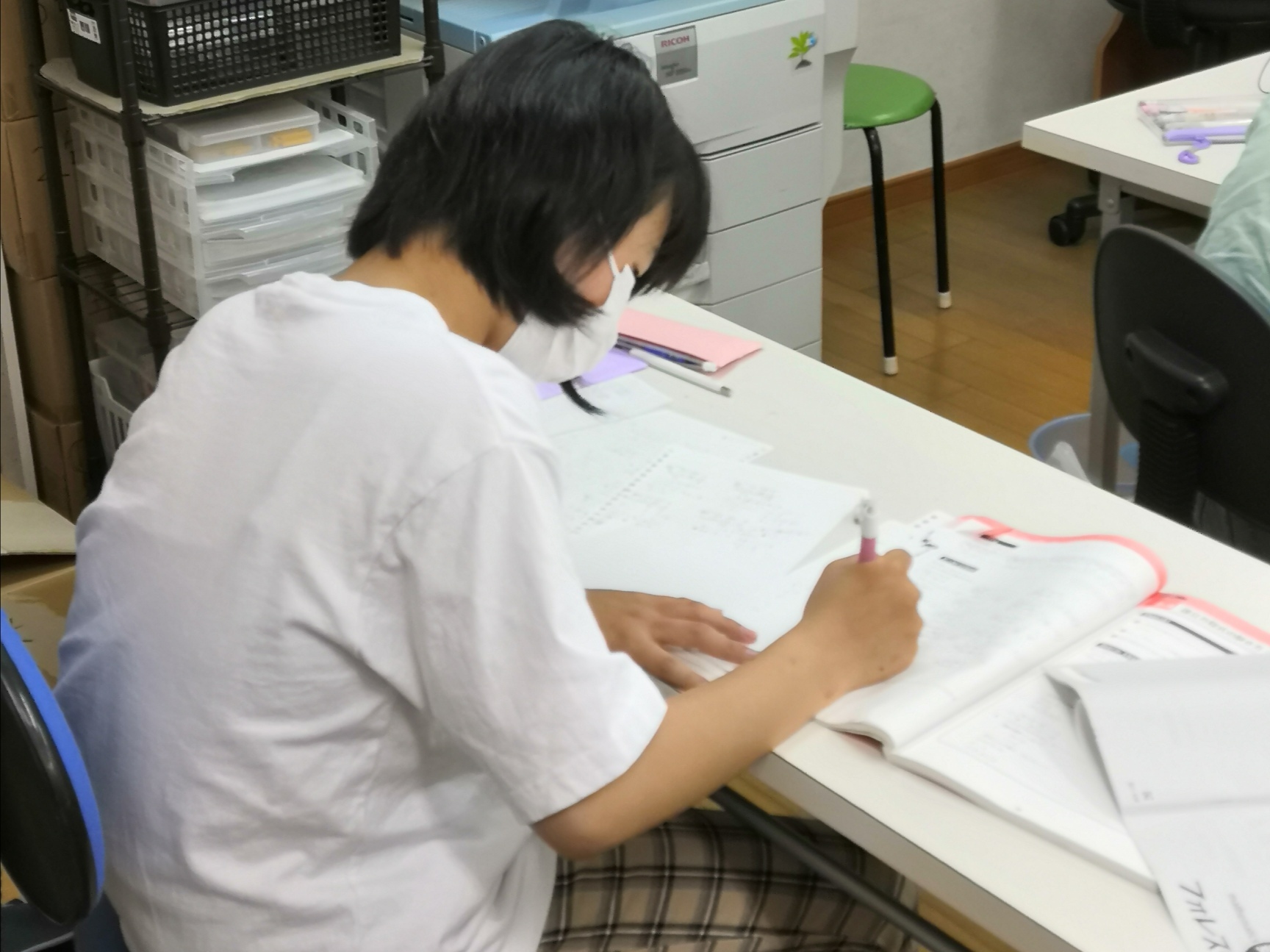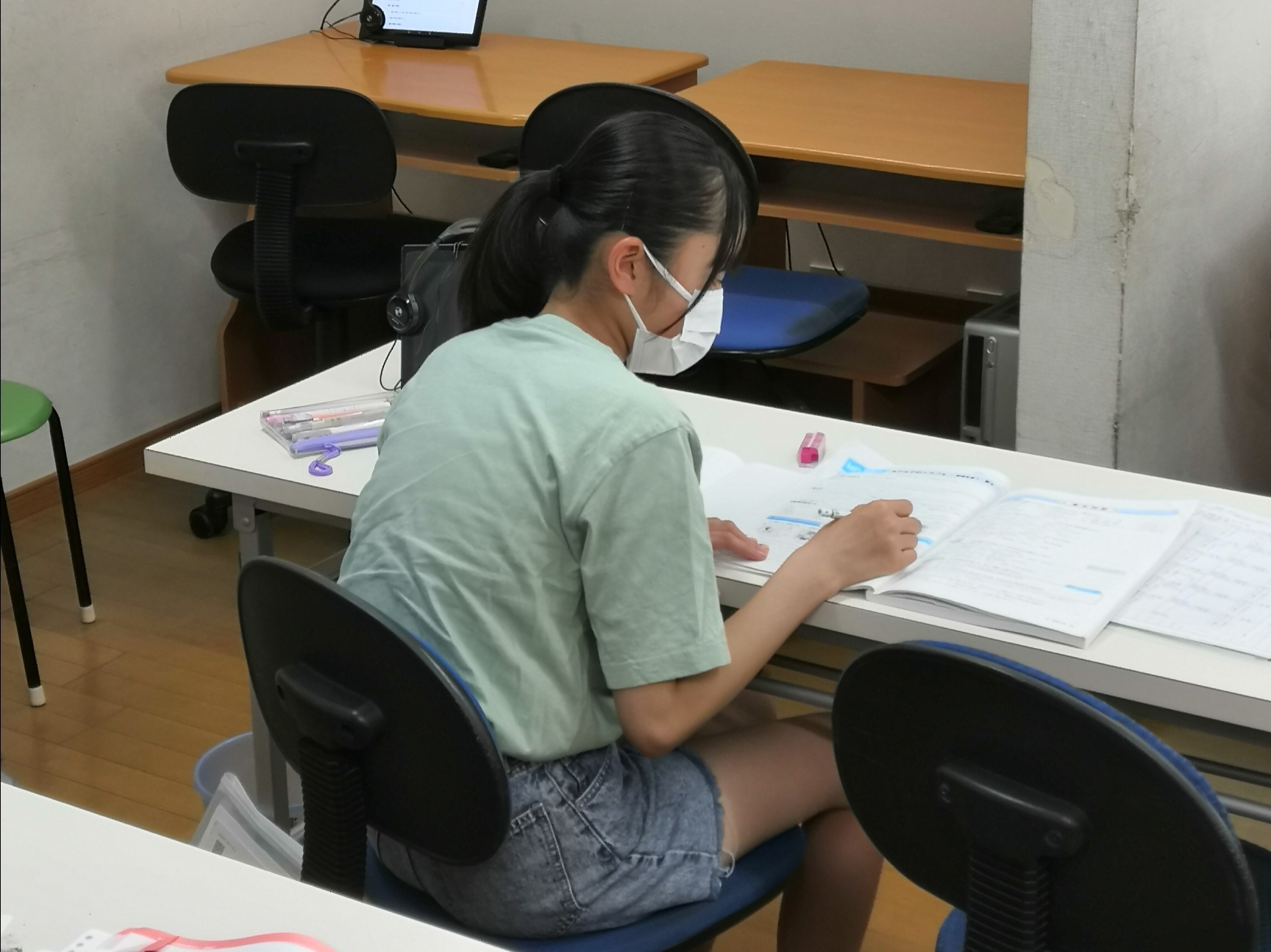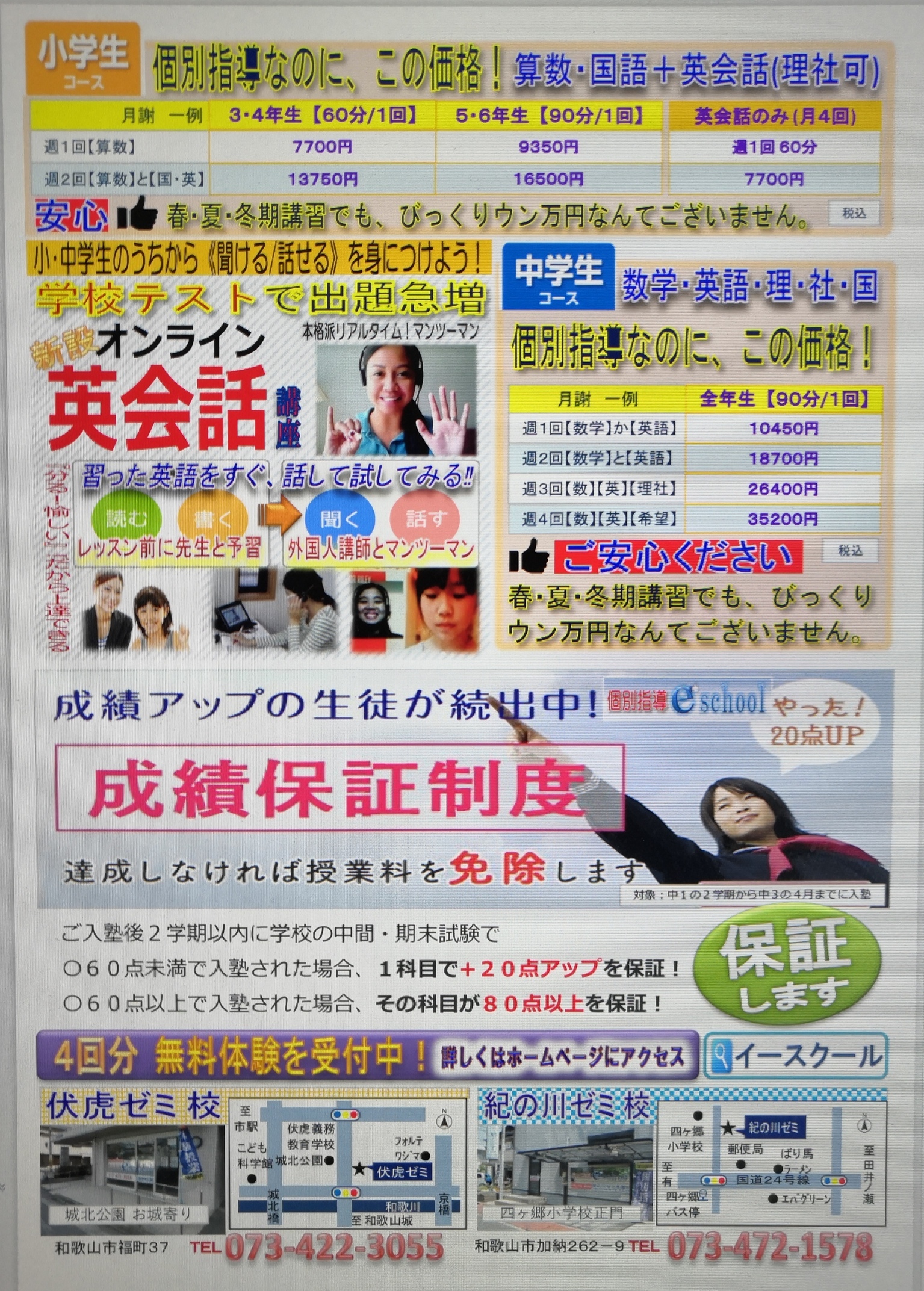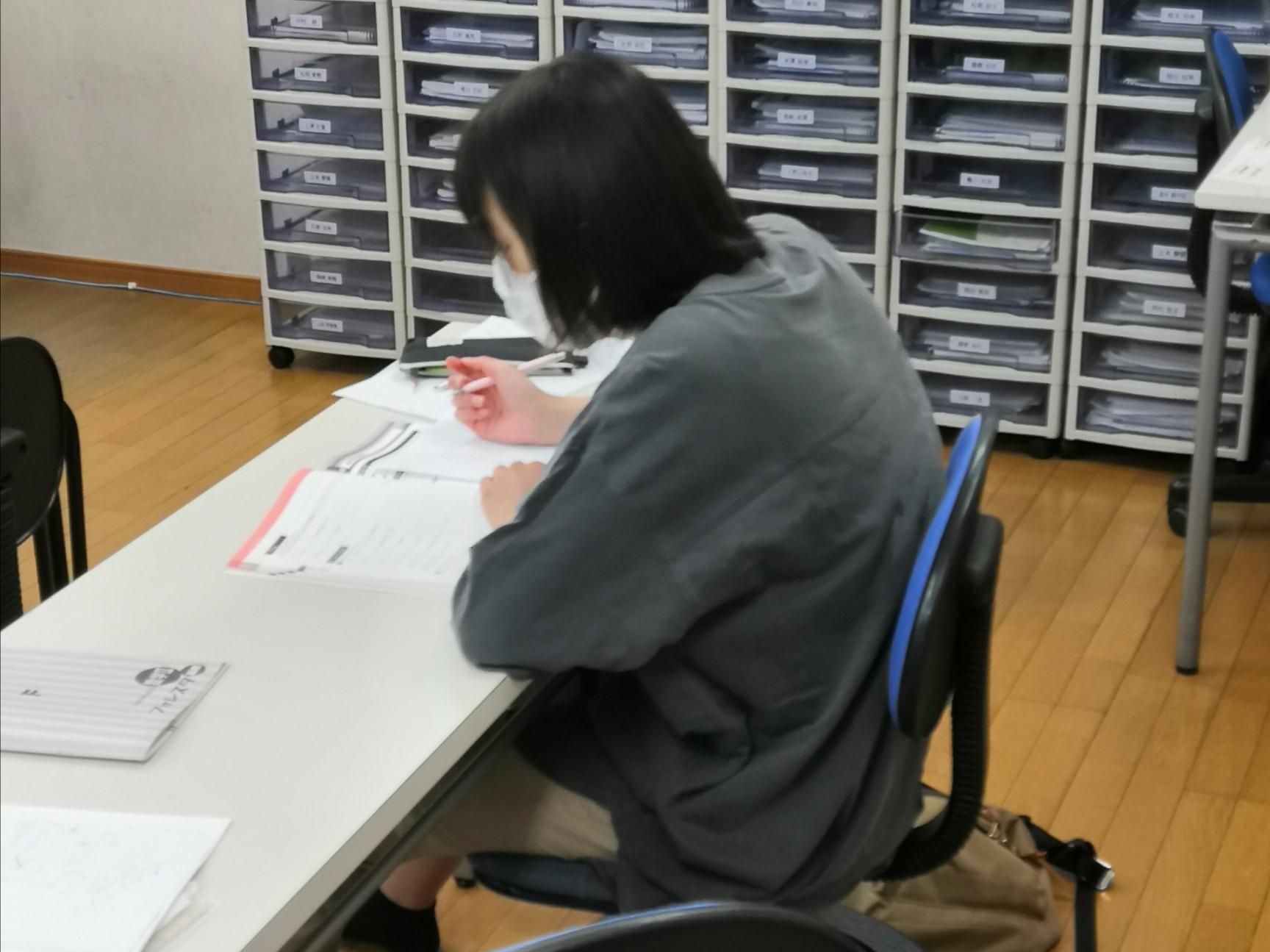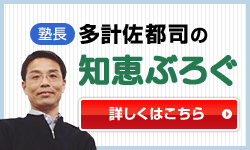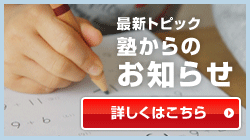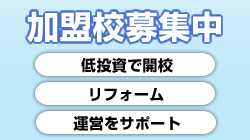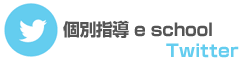おウチでできる、カンタン成績UP勉強法!②

英単語・漢字の暗記が苦手な子のために
保護者のみなさん
我が子にこんなこと思ったことありませんか
「ウチの子は、どうして、それくらい覚えられなのか?」
そんな我が子に、こんなこと言ったことありませんか
「書かないと覚えられないよ?」
もっともな意見ですよね。
でも、それでも書かせることで、ちゃんと覚えられるようになりますか??
現実は、なかなか一筋縄ではいきませんよねぇ。
そこで、まず何よりも、覚えられない原因をはっきりさせてあげないとダメです。
暗記している時の子供の様子を、よく観察したげてください。
①読み方をわかって、書いていますか?
②意味を理解して、書いていますか?
③ただ写しているだけになっていませんか?
これら3点に当てはまる子供は共通して、
実は「覚える作業とはどういうことなのか」をよくわかっていないのです。
そこで、≪暗記の鉄則3か条≫*お絵描きにならない!
①読み方を覚えさせる!
②意味をはっきりさせる!
③ただ単に写さない(見ないで書く)!
「な~んだぁ、当たり前だろ」と、あなどるなかれ!
結構、盲点ですよ。
暗記な苦手な子供にむかって「書いて覚えろ!」とよく言いますが、その方法まで指導する塾や親が果たしてどれほどか疑問です。
「覚えろ」と10回書かせても、隠すと書けない。
これって実は、子供に問題があるのだけでなく、教える側にも問題があるんだよなぁ。