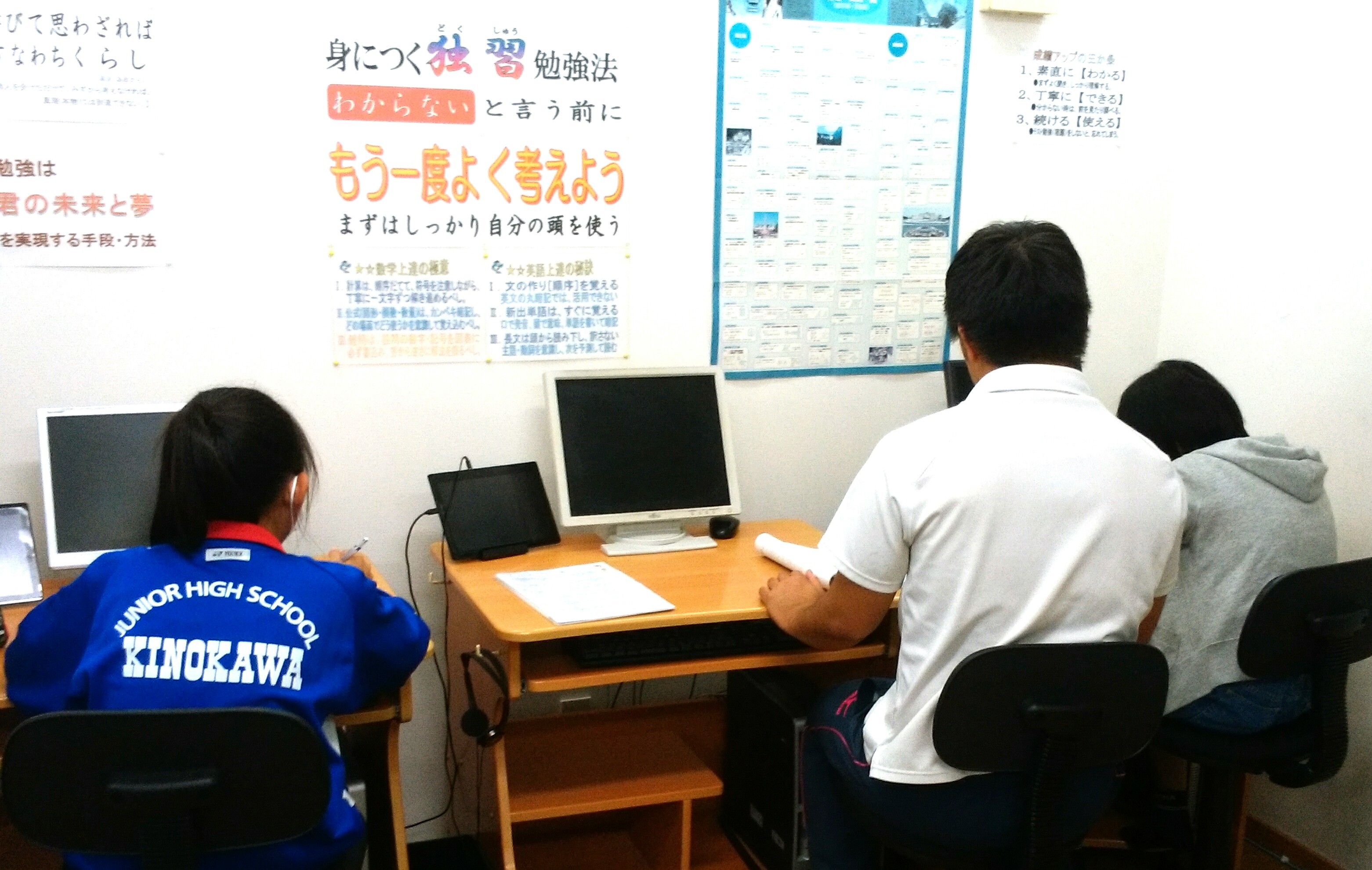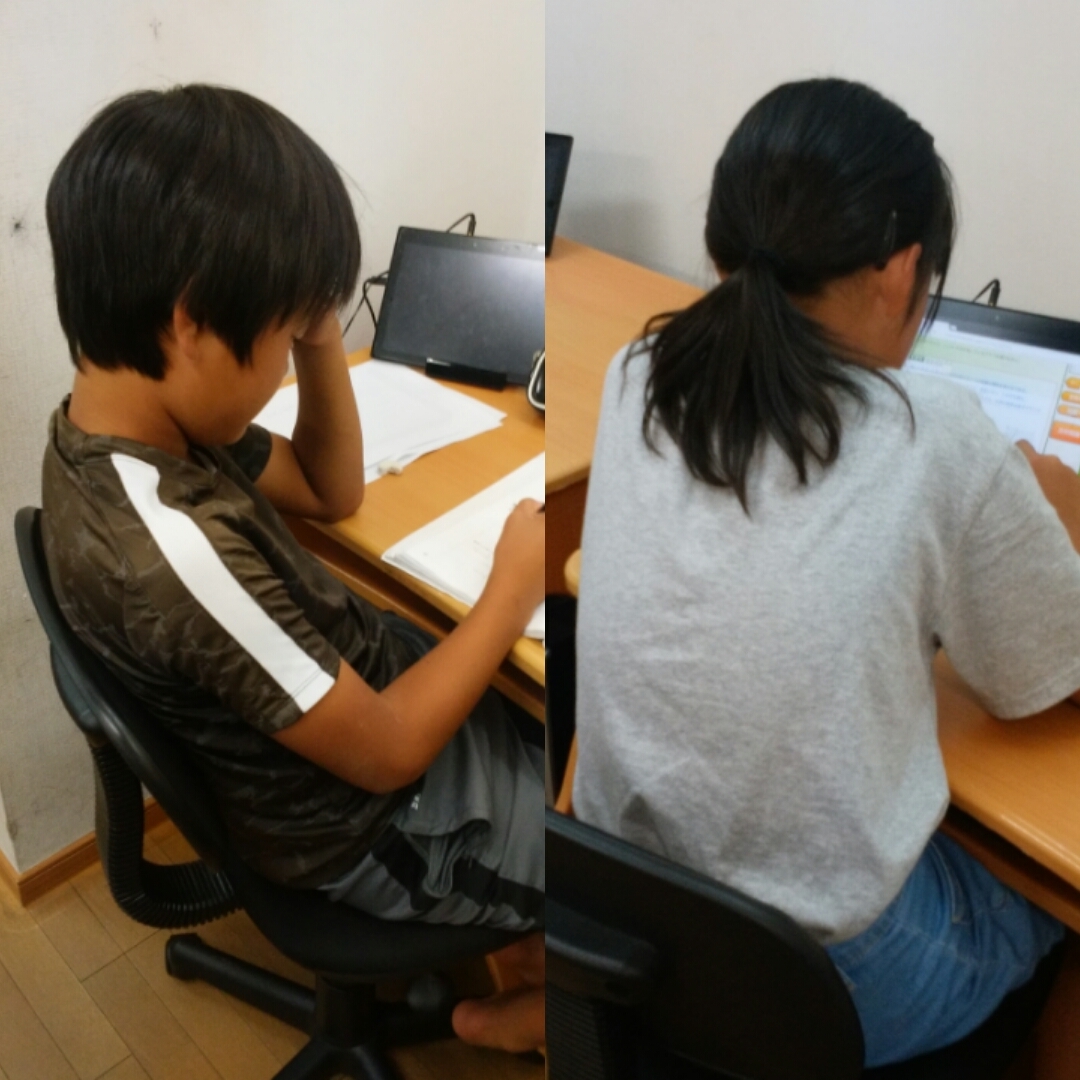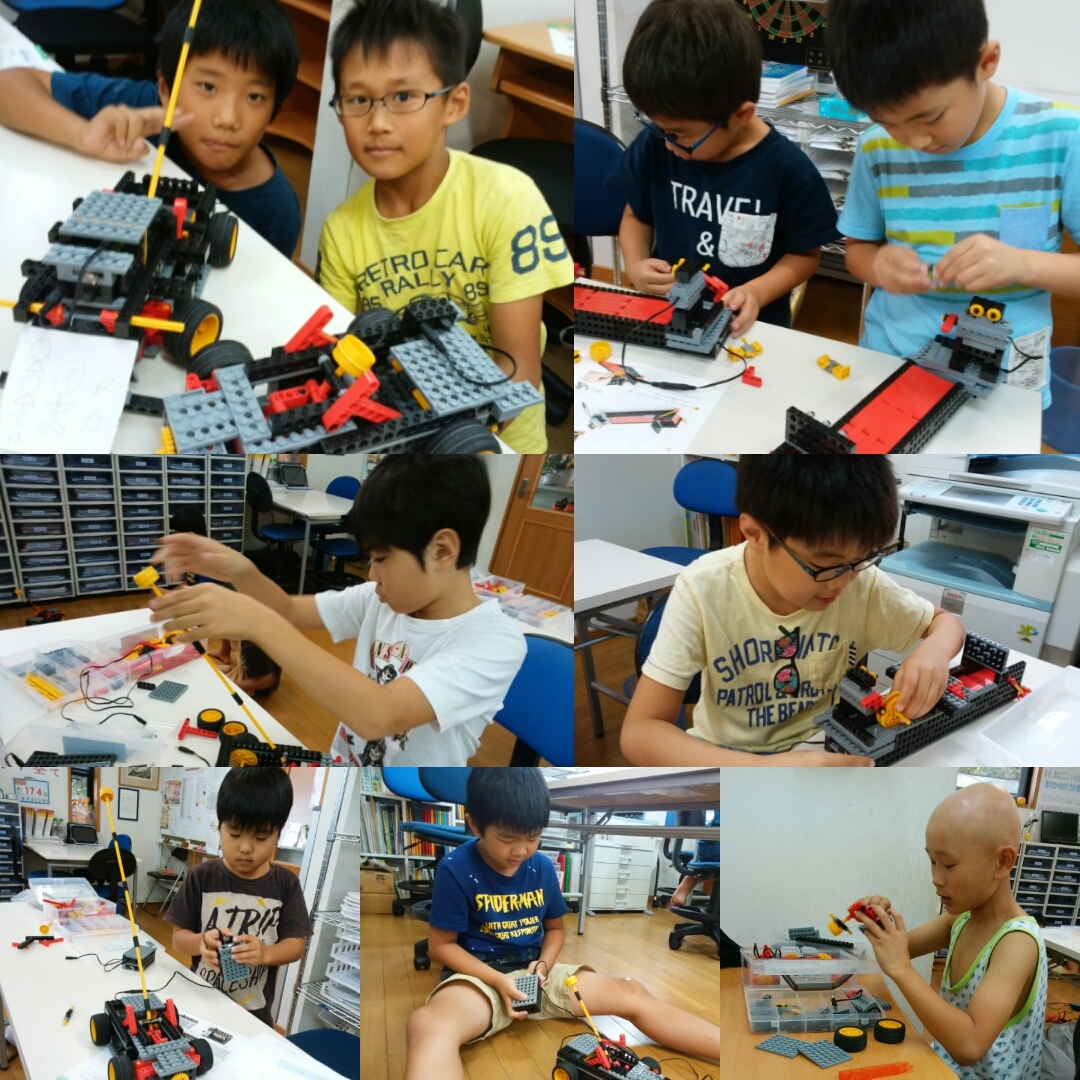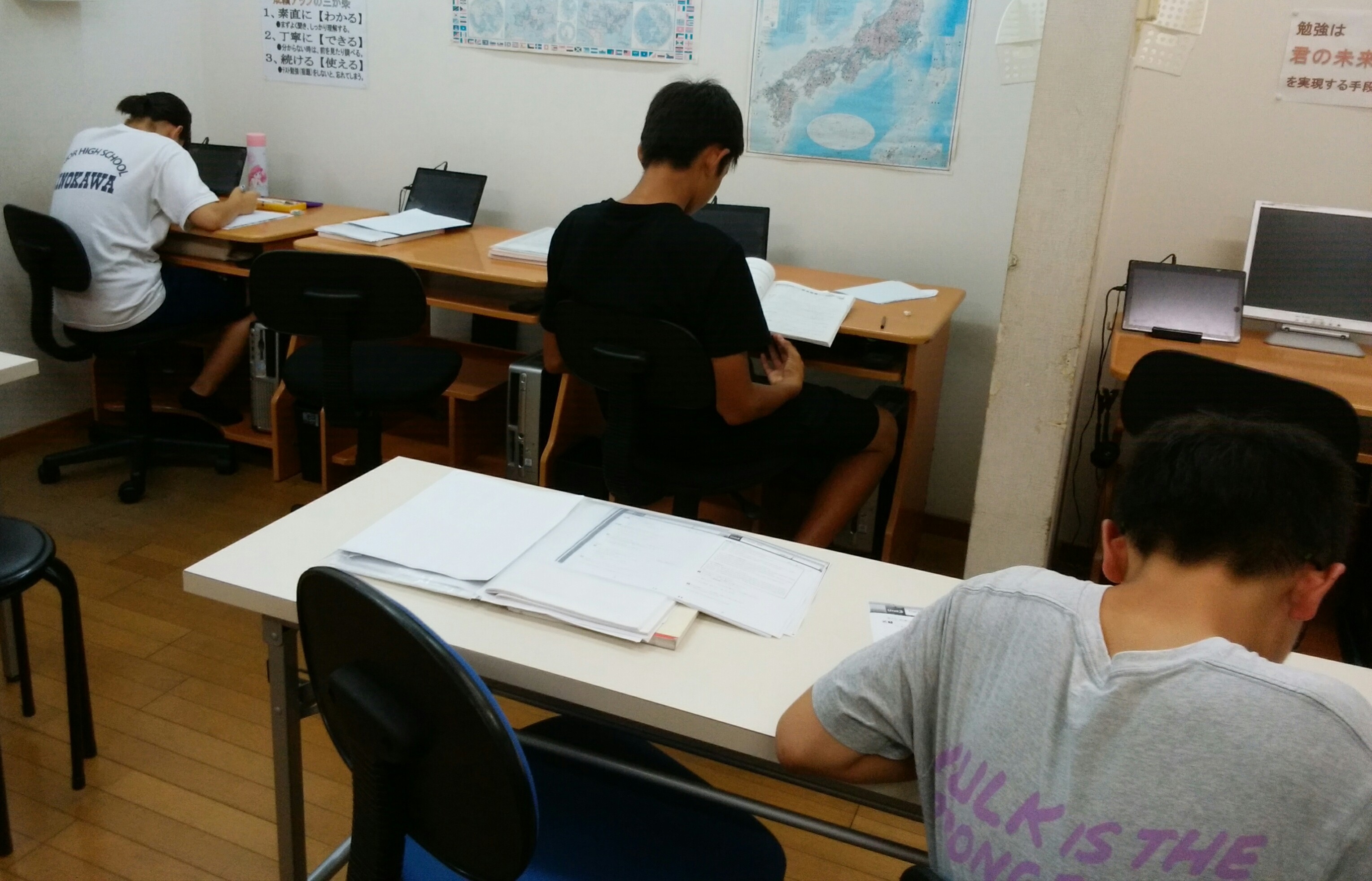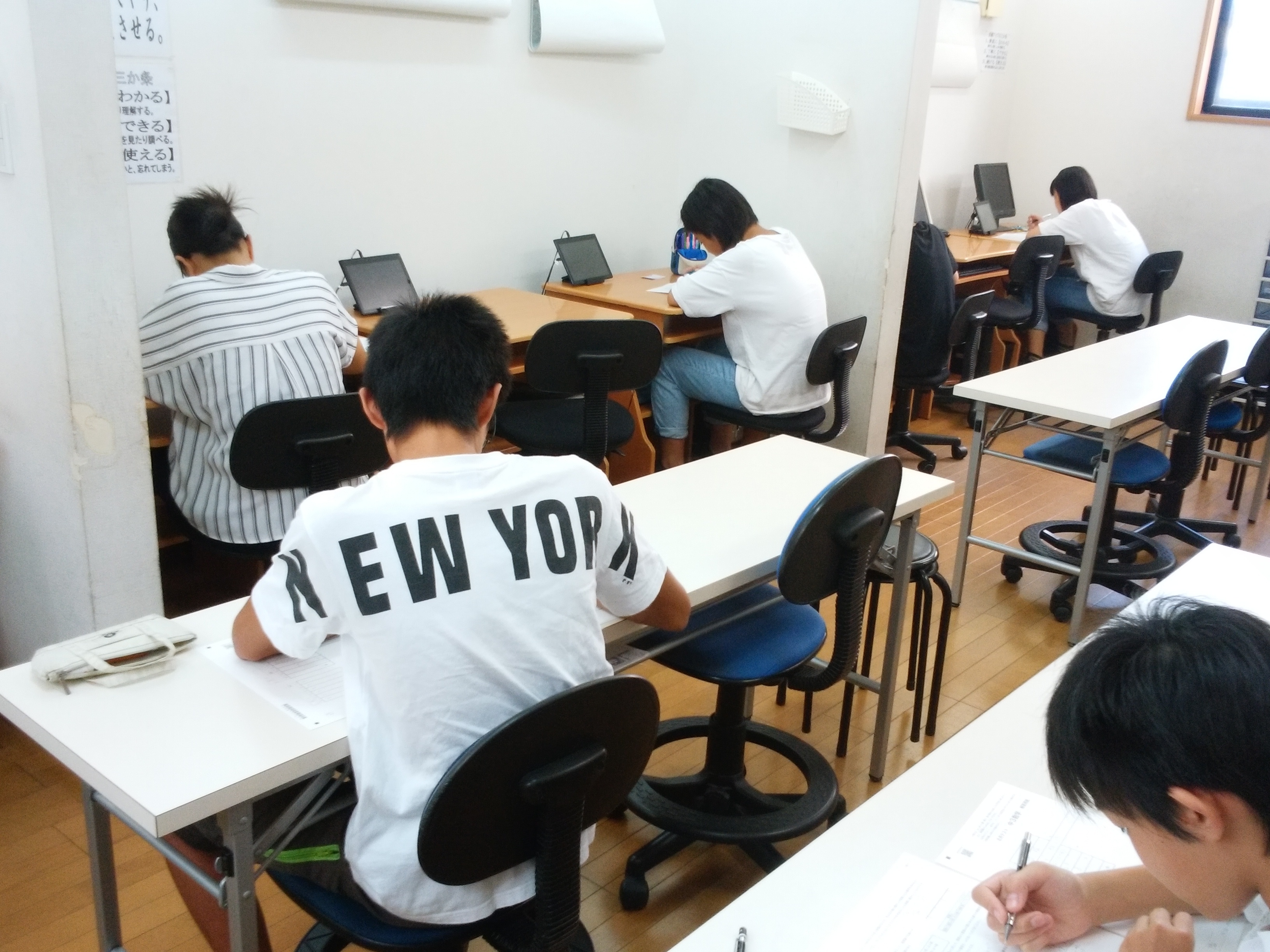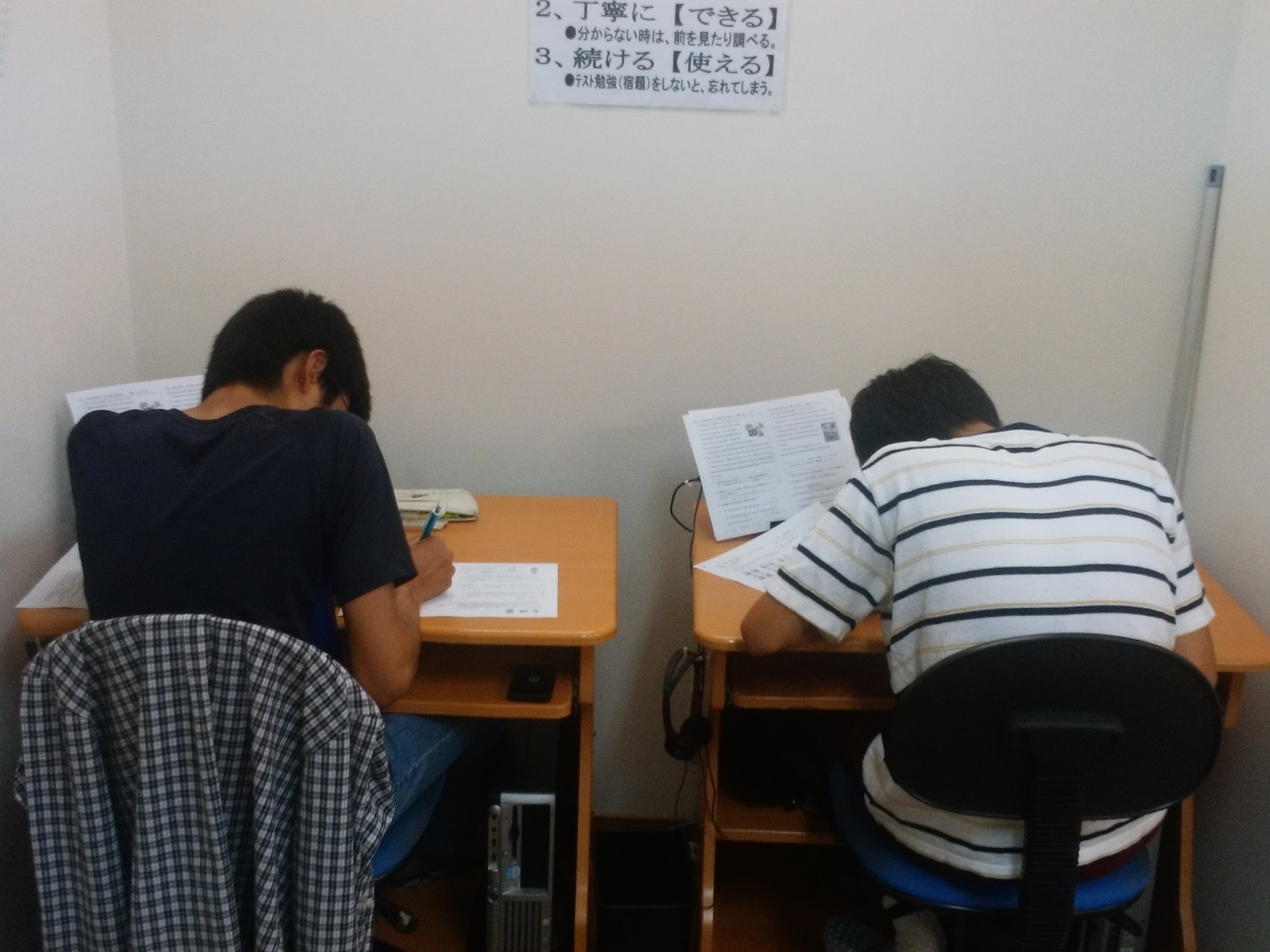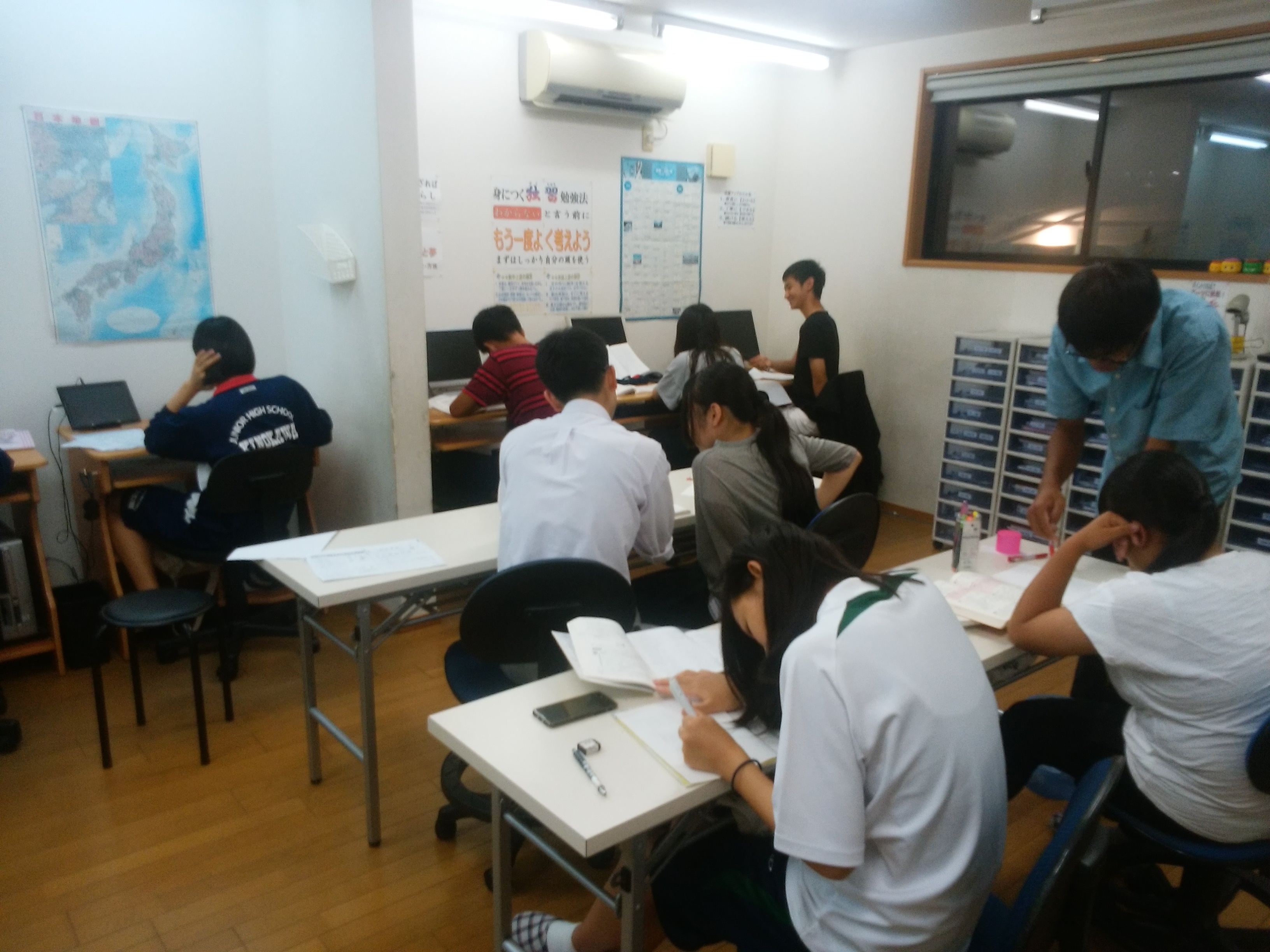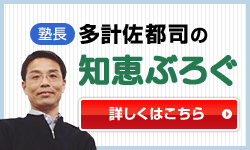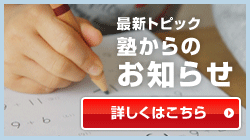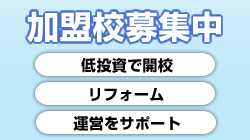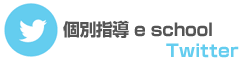前回は長い受験勉強を乗り切るためには、「どこどこ高校に入りたい」というモチベーションが必要だという話しをしました。
今回は、そのゴール(長期目標)に向けて、取り組み方についてです。
受験勉強も実は、定期テストの要領にやればいいよって前回言いましたよね。
具体的には日々の受験勉強の中に、中期目標ないし、短期目標を設定すれば、意外にスムースに勉強を運びます。
考えてみてください。定期テストのとき、範囲発表(日)があると、いついつに何の勉強をするという計画を立てましたよね。受験勉強も同じでそのスタイルを持ち込めばいいいいのです。
でも、してはいけないパターンについてお話しします。[今日は、何時から何時までこの教科。そして次は何時まであの教科]といった具合に、細切れ積め積めプランは絶対よくないです。一見、具体的でよさそうに見えますが、こんな計画を立てて、定期テストの時、うまく計画どおり行きましたか。もしこの方法でやってできていたとしたら、あなたはきっともう自分なりの受験勉強ができており、今悩んでいたりしないはず。このコツコツ詰め上げていくやり方は、長時間の受験勉強に慣れていないものにとって、[やった感]が非常に味わいにくく、計画倒れが落ちでしょう。
では、みなさんが定期テストの勉強でノリにノッて、はかどっている時って、どんなときでしたか。明日、数学のテストだって時に、範囲の問題集を「あと何ページだ!」と数えながら取り組んでいる時じゃなかったですか。
これはつまり、やったことが目に見えて進んでいくときです。受験勉強におきかえてみましょう。
毎日、受験勉強を始める前に、先に取り組みべき科目を絞り込み、問題集なら何ページまで必ずするんだと短期目標を決めること。あとはやるだけ。やっている内容はハードであっても、計画自体すごくシンプルなので、ページめくれる感覚が心地よく、やったことが見える化することで充実感を得れ、継続力を生みます。暗記科目であっても同じで、時間で区切るのではなく、参考書の範囲を決め、とことん頭が煮詰まるくらいまでした方が結果、受験勉強をやってるぞ感が湧いてきますよ。但し、手の届く範囲にスマホ放置は厳禁。
中期計画的には、科目ごとに参考書や問題集を一冊に絞り込んで、いつまで仕上げるぞという計画を立てるといいでしょう。やってダメなのは、ひとつの教科に何冊も同時に手を出すこと。これは先に述べたとおり、一見すごくよさそうですが、進捗状況がはっきりせず、凡人にとっては非効率に陥り、計画倒れを起こします。まずは目の前の一冊をいついつまでには終わらせるんだと計画を立てた方が、シンプルかつ進んだ感があり、継続できる力を生んでくれます。その一冊が終われらせてから、次の一冊に取り組むようにしましょう。
どうでしたか。少しは参考になったでしょうか。ではでは、ガンバレ、受・験・生!
2018年08月06日 14:47