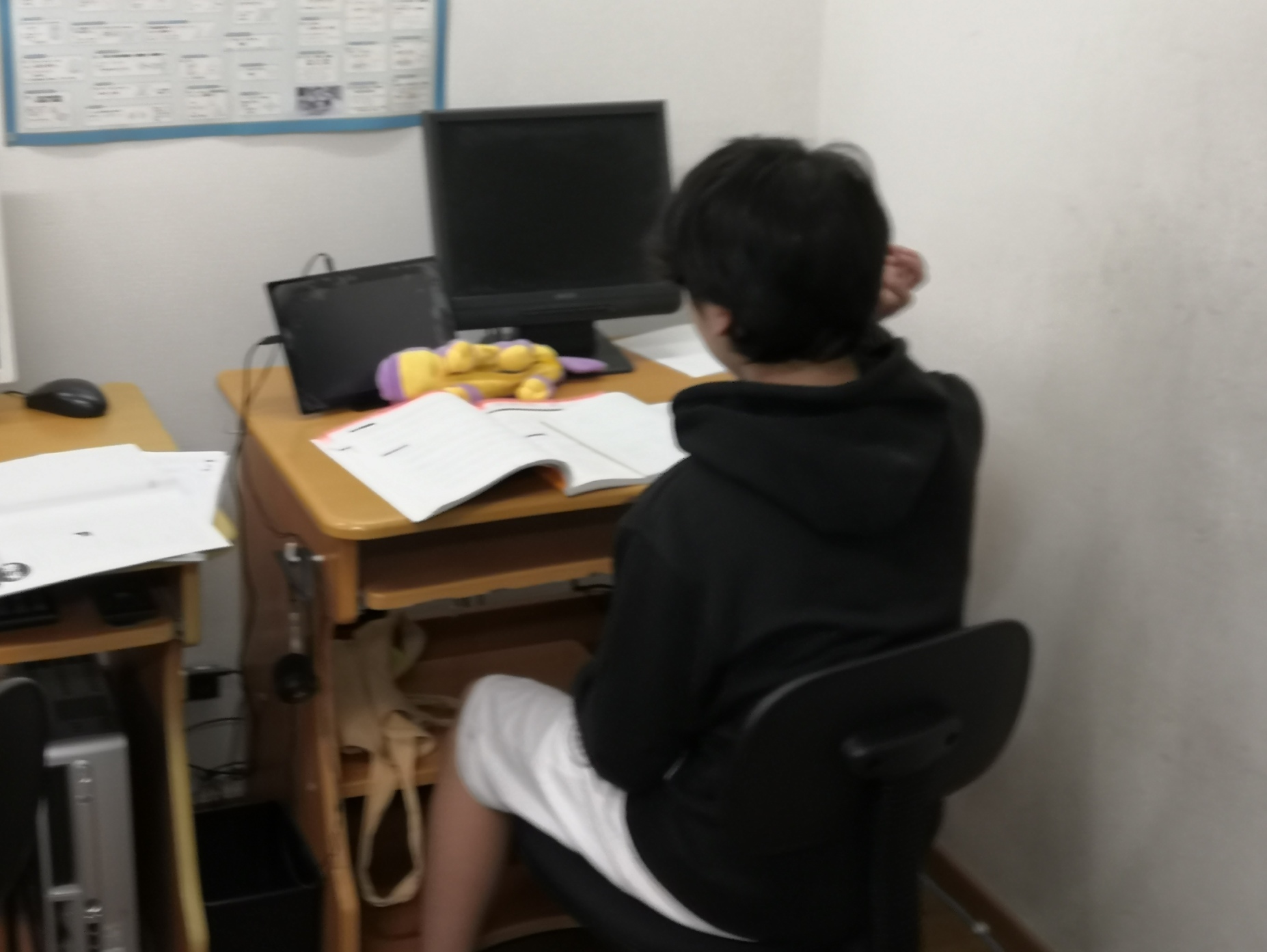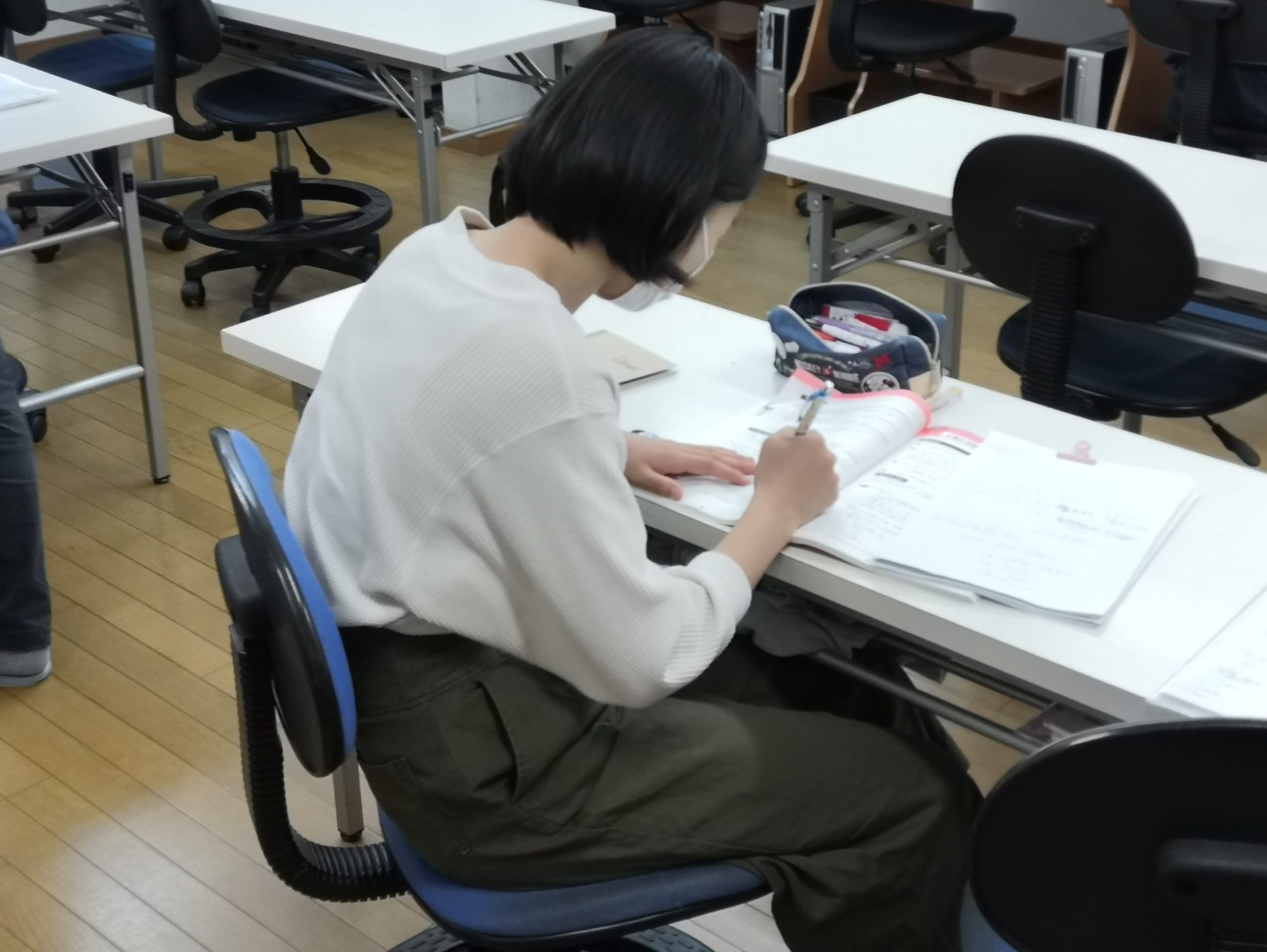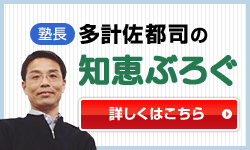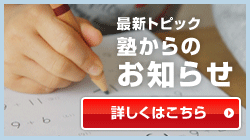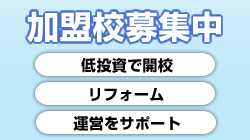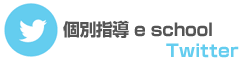国語が苦手な子へのメッセージ![和歌山市の個別指導イースクール]

そもそも国語力ってなんだろう?。
文章を読む力。
だから本を読むといい。
こんな意見が聞こえてきそうですが、これでは国語の成績は上がりません。
あまりにも漠然としすぎ、実際何を意識し実践すればいいのか見えてきません。
そんなみなさんはこぞって、国語ってそもそもなんであるかってことを忘れているか、あるいは知りません。
国語というのは、言い換えれば『言葉』ともいえます。
その言葉はなぜあるのですか。
相手に自分の考えを伝えたいからです。それが国語です。
そして、相手に自分の気持ちをしっかりと効果的に伝える方法として、大きくわけ3つの法則があります。
①【言い換える】具体的な例を添えたり、逆にポイントをまとめてすっきり述べる
②【比べる】よく似たもの、全く違うものを並べて、比較してみせる
③【なぜをたどる】なぜそうなるのかを、原因・理由を整理して述べる
これら3つをうまく活用し話したり書いたりすることで、相手を説得し、なるほどと納得してもらえます。
だから、作文の上手な人は国語力があるとも言えます。
国語の成績を上げるには、どんな問題集をやるよりもまず先に、これら3つの言葉(国語)の原則があることをしっかりと分かっていなければなりません。
私の塾でも夏休み以降、高校入試の国語に備え、文章題の読解テクニックを指導する特訓講座を組んでいますが、必ずまず最初に塾生たちには、文章を読む前に、国語(言葉)とはこの3つの法則からなっていることを意識付けします。
それだけでも、見えてくるものが全然違ってきます。
ただ漠然とか見えなかった問題が、何を問おうとしているのかはっきりと解るようになってきます。
だって、国語の問題なんてほぼ全て、これら3つ法則の問いかけなのですから。
これを読んでそうなんだと思えただけで、君の国語の実力10点アップしましたよ。
マジで!