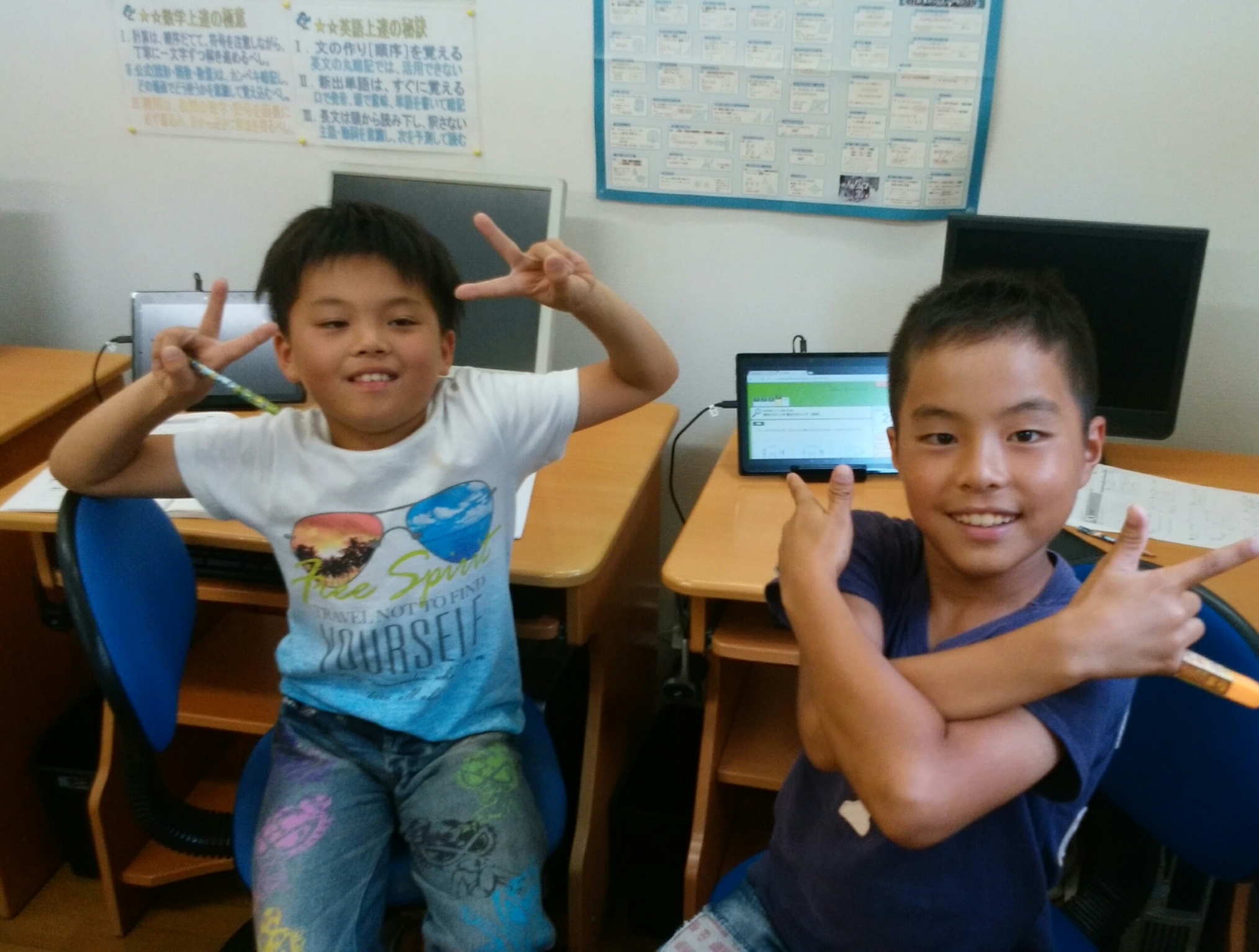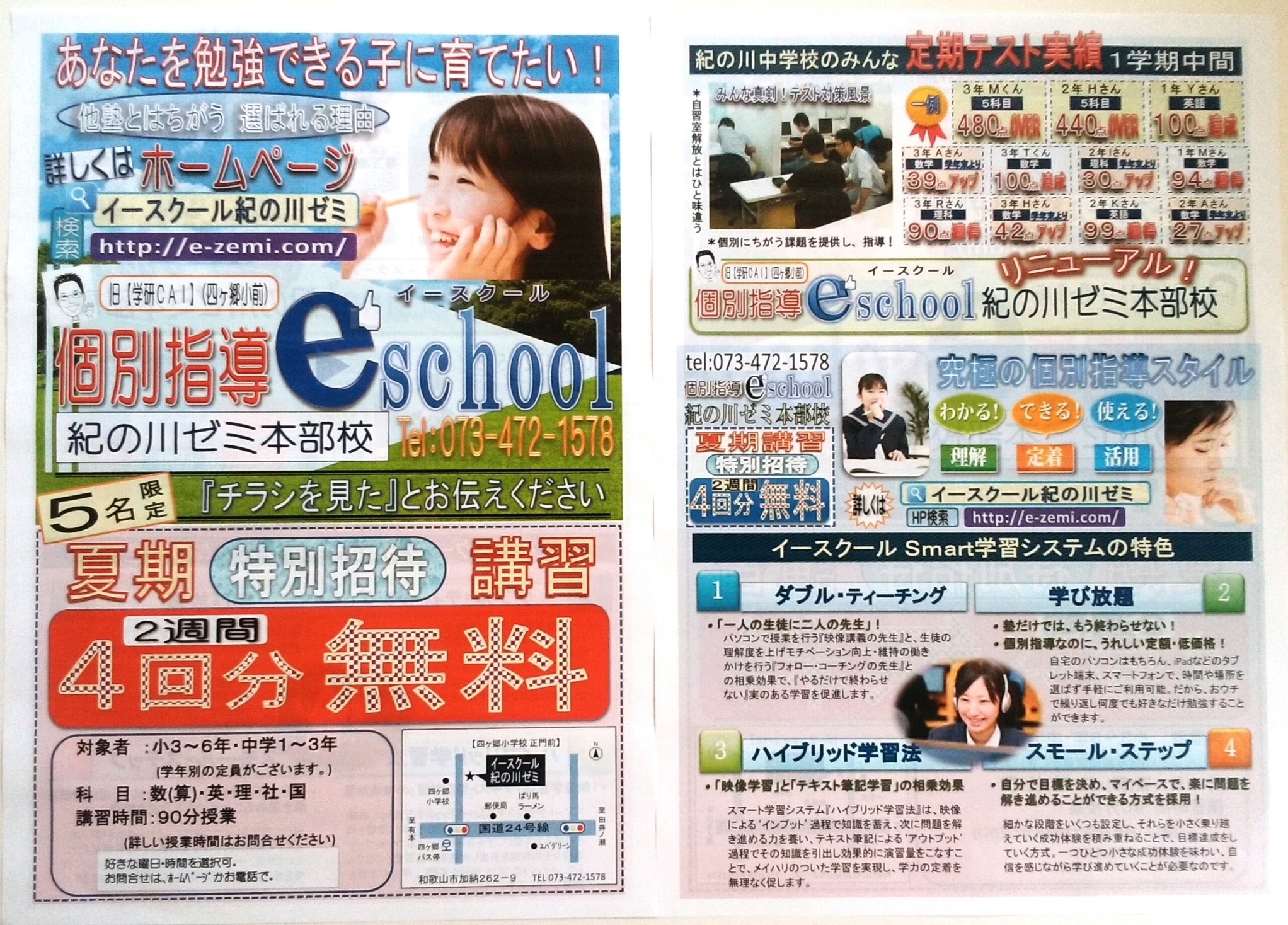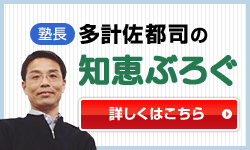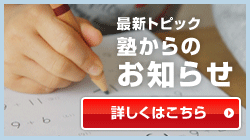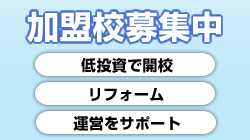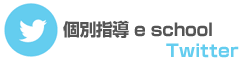⑤賢(かしこ)くならずにはいられない 【マル秘 勉強法】
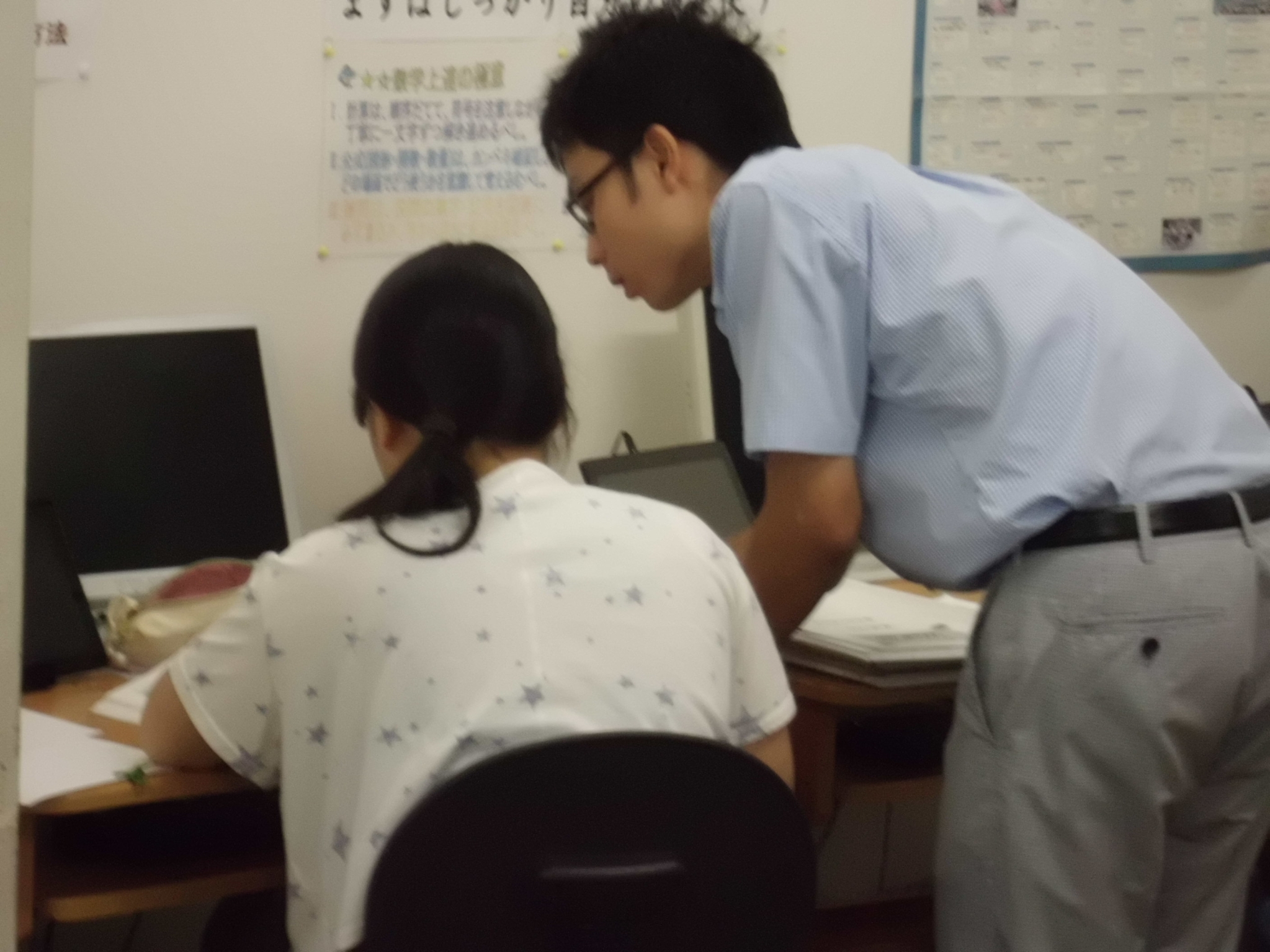
脳についてのお話しです。脳は、覚えるよりも忘れる方が得意だと知らずと分っていますよね。そして、いかに天才と言えども一生で、脳の記憶容量のほんの一部しか使用しません。だから、天才も我々のような凡人も脳の稼働領域には大差はなく、頭の良し悪しは、単に脳に記憶させることが他人よりも少しばかり上手かどうかという差にすぎません。
脳の特性を知り、うまく活用するだけで、記憶力が飛躍的に伸びると言えます。記憶するコツをいくつか紹介していきますね。
①『私は僕は、暗記が苦手だ』と悩むこと自体、脳科学的には記憶することの妨げとなるそうです。先ほど述べたとおり、誰も彼もみんな脳の大きさは同じなのですから、苦手だと思う暗示が脳活動を抑制しまうのです。『私はできない!』と思ってはいけません。
②効果的な暗記術とは、脳へにストレスをできるだけ無くし、時間的にも物理的にも無理なく、脳に覚えさせることがベスト。どういうことかというと、悪い例を挙げると一目瞭然。長期保存記憶として『一夜漬け』が最悪ですね。脳に記憶として残らず、非効率の極みであることは、みなさんご存じのはず。忘れてもいい記憶ならいっこうに構いません。受験に必要な科目、一夜漬けしていませんか?。ああ、なんてもったない、もったいない!。
③暗記は繰り返すことで脳への刺激となり、その記憶は増強されます。実は忘れてしまうという脳の機能は、その記憶の消去ではなく、潜在的な無意識の領域〔潜在記憶〕での保存だそうです。その記憶をアウトプットする方法は『復習』です。そして重要なことは、必ず1か月以内に復習すること。潜在記憶での保存期間が一か月で、それを過ぎると記憶に残りません。忘れてしまうのです。そこで実例をあげると、定期テストの間隔を考えてみてください。1か月以上ありますのね。理科と社会をテスト前に勉強しようとしても、何もしないと全く覚えていませんよね。ですから、1から覚え直しをしないためにも復習を一か月以内にすることです。
④暗記は繰り返すことで、その記憶は増強されると言いました。その観点からひとつ。受験勉強で、参考書をいくつも購入し手を出す人がいます。やる気はすばらしいことですが、それも脳科学的には非効率です。どれがよいのか分からないくらい色々と参考書が売られていますが、多少の良し悪しはあれ、内容には大差ありません。ですので、どれか一冊でけっこう、同じ参考書で何度も暗記作業を繰り返し、どのページにどの内容があるか思い出せるくらい学習した方が、脳科学的にも記憶力として絶大な効果を発揮します。
また続き、ご期待ください!